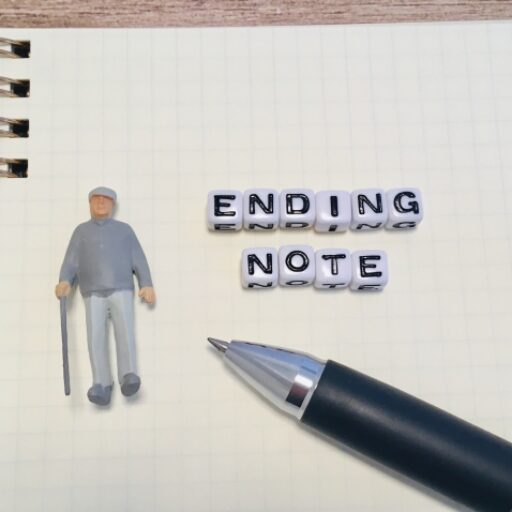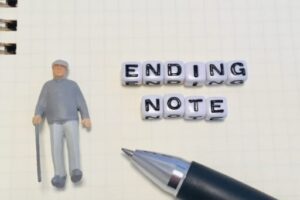最近よく耳にする「エンディングノート」。
終活を考え始めた方にとって、まず手に取りやすいアイテムです。
けれど、いざ書こうと思って書店や通販サイトで探してみると、種類が多すぎて「どれを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いはず。
この記事では、エンディングノートを購入する際の選び方や、目的に応じたおすすめ商品をご紹介します。
無料テンプレートや自作との違いも解説しているので、初めての方も安心してご覧ください。
目次
そもそもエンディングノートってなに?
エンディングノートとは、人生の終わりに向けて「自分の情報」や「希望」、「思い」を書き留めておくノートのことです。
遺言書のような法的効力はありませんが、家族や周囲の人たちが困らないように、さまざまなことを整理できます。
記載内容は個人情報、持病や介護の希望、財産や口座、保険の情報、葬儀やお墓の希望、そして家族へのメッセージなど。
人生の記録帳とも言える存在です。
購入するメリットとは?無料でいいんじゃないの?
確かに、インターネットには無料でダウンロードできるエンディングノートのテンプレートもあります。
また、自分でワードやノートに書き出すこともできます。
しかし、市販のエンディングノートには次のようなメリットがあります。
まず、内容がとても整理されていて書きやすいという点。
質問形式やガイド付きで、何をどこに書けばいいのか迷わずに済みます。
また、製本されているので保存しやすく、紙の質もしっかりしています。
長年保管しておくことを前提に作られているため、将来的にも安心です。
さらに、最近はデザインや表紙もおしゃれなものが増えていて、「書いてみよう」という前向きな気持ちになれるというのもポイントです。
初めての方におすすめのエンディングノートはこれ!
実際にどんなエンディングノートを選べばよいのでしょうか。
「書いて安心 エンディングノート」(主婦の友社)
その名の通り、「安心」して記入を進められるように工夫されたエンディングノートです。
主な特徴は以下の通りです。
シンプルで使いやすいデザイン: 複雑すぎないシンプルで落ち着いたデザインで、誰でも抵抗なく手に取れるよう配慮されています。
読者に寄り添った丁寧な構成: 主婦の友社という出版社ならではの視点で、エンディングノートを初めて書く人や、何から書いていいか分からない人でも挫折しにくいよう、非常に分かりやすく、優しい言葉でガイドされています。
「書き方」への配慮: 単に項目を並べるだけでなく、各項目の「なぜ書くのか」や「どう書けばいいのか」といった具体的なヒントやアドバイスが充実しているのが特徴です。迷いやすいポイントには、記入例やQ&Aなどが豊富に盛り込まれています。
幅広い項目を網羅: 自身の情報、医療・介護の希望、財産、葬儀、お墓、デジタル情報、大切な人へのメッセージなど、もしものときに家族が困るであろう必要な情報をバランス良く網羅しています。
心情的な側面への配慮: 事務的な情報だけでなく、家族や友人への感謝の気持ち、伝えたいことなど、心温まるメッセージを残せるスペースも確保されており、精神的な安心感も得られます。
コクヨの「もしものときに役立つノート」(エンディングノート)
文具メーカーならではの工夫が凝らされた、使いやすさと実用性を兼ね備えたエンディングノートです。
主な特徴は以下の通りです。
- 網羅性の高い項目: 自分の基本情報から、預貯金、保険、クレジットカード、デジタル資産(ID・パスワードなど)、医療・介護の希望、葬儀やお墓のこと、大切な人へのメッセージまで、「もしものとき」に家族が困るであろう情報を幅広く網羅しています。
- 実用的な構成: 複雑な内容を分かりやすく項目分けしており、誰でもスムーズに記入を始められるよう工夫されています。**「今日からすぐに書き込める項目」**が多いのも特徴で、終活初心者にもおすすめです。
- 高品質な紙質と製本: 長期保存に適したコクヨオリジナルの**「コクヨ帳簿紙(特厚口)」**が中紙に採用されており、なめらかな書き心地で裏写りしにくく、耐久性も優れています。製本は「かがりとじ」で、ページが開きやすく書き込みやすいです。
- 便利な付属品: CD-Rを1枚保管できるディスクケースや、証明写真などを入れられるポケットが付いており、関連する物理的な情報も一緒に管理できます。
- 日常使いも想定: 「もしものとき」だけでなく、銀行口座や保険の情報を整理したり、連絡先をまとめたりと、日常生活の備忘録としても活用できるように作られています。
シンプルながらも必要な情報がしっかり詰まっていて、「文具として」の使い心地の良さが際立っているのがコクヨのエンディングノートの大きな特徴と言えるでしょう。
江崎正行さんが監修している「もしものときのエンディングノート」
弁護士である江崎さんの専門知識が活かされているのが大きな特徴です。
具体的には、
分かりやすく整理されている: 専門家ならではの視点で、複雑な内容も分かりやすく、体系的にまとめられていることが期待できます。
法律や手続きに強い: 相続や財産管理、遺言書のことなど、法律や実際の手続きで家族が困らないような情報がしっかり盛り込まれています。一般的なエンディングノートよりも、トラブルを避けてスムーズに進めるためのアドバイスが多いと考えられます。
現代の生活に対応: インターネットやSNSのパスワードなど、デジタル資産の整理についても、現代のニーズに合わせて細かく記入できるようになっている可能性が高いです。
家族への配慮が深い: 弁護士として、多くの家族が直面する困りごとを見てきているので、「残された家族がどうしたら困らないか」という視点で、必要な情報が網羅されています。
市販と無料、自作の違いとは?
市販のノートは、デザインや構成、保存性の面で優れています。
一方で、無料テンプレートや自作はカスタマイズの自由度が高く、自分の書きたい内容に合わせて作ることができます。
「初めてでどう書けばいいかわからない」「長く保管したい」「家族にも見てもらいたい」という方には、市販のノートの方が安心でしょう。
一方で、「まずは書くこと自体に慣れたい」「形式にとらわれず自由に記録したい」という方は、無料テンプレートから始めてもよいと思います。
どう選ぶ?エンディングノートのチェックポイント
いろんな商品がある中で、どのエンディングノートを選べばいいか迷ったときは、次の3つを意識してみてください。
まずは「自分が書きたいことが含まれているかどうか」。
たとえば医療の希望をしっかり書きたい人もいれば、家族へのメッセージを重視したい人もいます。
次に、「自分にとって書きやすいかどうか」。
文字の大きさや行間、書くスペースの余裕など、実際に記入する場面を想像して選ぶのが大切です。
そして、「デザインが好みに合っているか」。
これは意外と大切なポイントで、気に入った見た目のノートだと書く気持ちも前向きになります。
自分の人生を映すノートですから、気持ちが明るくなるものを選びましょう。
まとめ:あなたにぴったりの一冊から終活をスタート
エンディングノートは、人生を振り返りながら、これからの暮らしに備える大切なツールです。
悲しいもの、怖いものではなく、「これまでを大切にし、これからを安心して過ごすため」の前向きな記録です。
ぜひ、自分に合ったエンディングノートを一冊選んで、今日から少しずつ書き始めてみてください。
家族への愛情や、自分の想いがきっと形になります。